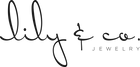「自分の歩みを信頼し、未来を切り開く。」ー lily & co. お客さまの物語 Vol.3
絵本作家として、そして2歳のお嬢さまの母として、日々の暮らしの中からインスピレーションを紡ぎ出しているYUKIさん。
ゆきさんが描かれる世界には、読む人の心をそっとあたためてくれる優しさがあります。
今回は、彼女の作品づくりや子育てへの思い、そしてインスピレーションの源についてお話を伺いました。
1. 自己紹介とライフスタイルについて
普段はどんな1日を過ごされていますか?
仕事が終わったら娘を迎えに行き、買い物をして帰宅。おやつを食べて、夕飯を作り、お風呂に入って寝るという毎日です。野菜は毎週、畑から土のついたまま届くので、買い物はお魚やお肉だけで済ませています。
繰り返しのようでいて、娘と過ごす日は予定通りにはいきません。
絵本を「読んで!」と何度も読んだり、英語のDVDをギリギリまで観たり、ベランダで砂遊びが始まる日もあります。だからこそ、時間にゆとりを持ち、いつでも柔軟に動けるように心がけています。
子育てとご自身の時間、どのようにバランスを取っていますか?
特に「バランスを取ろう」と意識してはいません。絵本作家の仲間で虐待防止に取り組む友人が、「子どもは宝物だから、家庭や地域、いろんな人の手で育てていけばいい」と言っていたのが印象に残っています。
独身の頃からその価値観に触れていたので、「母親がすべて担わなければならない」という思い込みは、あまり持っていませんでした。教育者のマリア・モンテッソーリも、幼い我が子の養育を人に任せていたと知って、母親としてどうあるかは人それぞれだと感じました。
私の場合、0歳の間はとにかく肌を密着させ、娘の五感を通して「安心できる場所がある」という感覚を育てることを大切にしました。そして1歳からは、夫や義母に養育を任せ、私以外との信頼関係を築けるように意識しました。
今の娘は、私と過ごすか他の人と過ごすか、自分で選べる状態です。そのおかげで、自然と自分の時間も持てています。
出産を経て思うのは、母親が子どものために一番できるのは、実は妊娠中かもしれないということ。お腹の中にいるときは自分の栄養が直接届きますが、産まれた瞬間から、子どもは子どもの人生を歩み始める。母親にも母親の人生があって当然です。
「バランスを取る」というよりも、お互いが自分の人生を生きているという感覚で暮らしています。私は娘を育てているというより、地球や社会に育ててもらっているのだと感じています。
ヨガやお菓子作り、文章を書くことなど、日々の暮らしの中でどんな時間が自分らしさを感じさせてくれますか?
やはり、クリエイティブな活動をしているときに最も自分らしさを感じます。最近では、大好きな食器店のテーブルコーディネート講座に参加したのですが、その時に使われていた国産の上質なリネンのテーブルクロスがとても気に入って。とろんとした手触りに癒され、これが日常にあったら幸せだなと感じたんです。
そのクロスを家のテーブルに敷き、アアルトのフラワーベースに花を飾るようになってから、「今日はどんな花を?」「どんな料理をどんなお皿に?」と考える時間が、とても楽しくて、自分らしくいられる大切な時間になりました。
こうした小さなときめきが、日々の暮らしを豊かに、私らしく彩ってくれている気がします。たとえば、結婚祝いにいただいたバーレイのティーカップに合わせて、英国展で買ったティーポットを使い、自宅でアフタヌーンティーを楽しむひとときも、私にとっては贅沢で満たされた時間です。

2. 創作活動について
絵本作家という道を選ばれたきっかけを教えてください。
東京の美術大学に通っていた頃、教育や心理学にも興味があり、どんな仕事が自分に合うのか迷っていました。そんな中で就いた子ども服デザイナーの仕事では、目に見えるものを作るより、人の心に触れるような制作がしたいと感じるようになりました。
未練もあって泣きながら退職を申し出ましたが、その後は保育について学びながら、自分の活動を模索することに。大学では立体作品を制作していましたが、ポートフォリオを振り返ると「人とのつながり」がテーマになっていたと気づきました。机に向かうより、興味のあるところへ足を運んで感じたことを作品にするスタイルがしっくりきたんです。
幼稚園で絵画造形教室の講師をしたり、東日本大震災の後は福島のチルドレンズミュージアムでのワークショップにも毎年関わってきました。そんな風に、思いつくことを試していく中で、一番「向いている」と言われたのが絵本作家の仕事。私自身、「絵本作家になろう」と強く決めたというより、自然とその道に導かれた感覚なんです。
文章を書くときに大切にしていることや、心がけているリズム・感覚はありますか?
文章を書くときに最も大切にしているのは、「嘘をつかない」ことです。自分の視点では真実でも、多角的に見ると伝わりにくかったり、矛盾が生じたりします。だからこそ、事実に基づき誠実に書くことを心がけています。
物語のテキストでは、自分の感覚だけに頼らず、他の人に読んでもらいながら推敲を重ねます。言葉の力を信じつつ、限界も感じているので、言葉で伝えきれない気持ちを表す方法として「物語」があると思っています。
また、文章を書く目的や、読む人の年齢・気持ちを意識することも大切にしています。何を、誰に伝えたいのかを明確にし、そのうえで言葉を選んでいます。
絵本づくりのアイデアやインスピレーションは、どんな時に生まれることが多いですか?
絵本のアイデアは、自分の中にある“絵本の種”のようなものを編集者さんが見つけてくれて、「これを絵本にしてみたら?」と客観的な視点からアドバイスをもらうことがきっかけになることが多いです。
「絵本を作ろう!」と意気込むと、逆に独りよがりになってしまう気がしていて。絵と文があれば絵本にはなりますが、読者の気持ちを想像しながら作るには、人の意見を聞きながら形にしていくことが大切だと感じています。
作品によっては何度も描き直して、最初のアイデアとは全く違う仕上がりになることもあるんですよ。
以前、テディベアと女の子が登場する作品を拝読し、とても印象に残っています。そのお話が生まれるまでの背景や、どんな想いを込めて描かれたのか、ぜひ教えてください。
『まぁちゃんのテディベア』読み聞かせYoutubeはこちら読んでくださってありがとうございます!
もしよければ、メ〜テレさんが制作してくださった読み聞かせ動画もぜひご覧ください。絵本を読んでくださった方にしか伝わらないエピソードも出てきますので。
この物語は、京都の絵本教室に通っていた頃に生まれました。
最初は、ぬいぐるみのくまを持つ女の子がショーウィンドウのうさぎに惹かれ、くまが嫉妬する…というお話でしたが、先生の「ぬいぐるみではなく犬にしたら?」というアドバイスから、テディベアと犬が登場する形に進化していきました。
当時、自分の絵柄が定まらず悩んでいた私は、メアリーブレアの絵本を参考に描いたところ大きな反響がありました。ただ、人の真似ではなく、自分らしい表現で描きたいという想いが強くなり、絵本を描き直すことにしました。
「きみは ぼくの たからもの」という言葉がふっと浮かび、それがこの物語のテーマなんだと気づいたんです。
“たからもの”ってどうやったら伝えられるんだろう? そう考えながら、登場人物の嫉妬や不安といった感情にも丁寧に向き合いました。
実はこの絵本、私自身の幼少期の感情と深く結びついているんです。
私は弟と妹がいる長女で、「お姉ちゃんだから」と甘えられず、もっと母にぎゅっとしてほしかった…という想いを抱えていました。その感情が、テディベアの視点に重なっていったんですね。
テディベアが見ている女の子は、私にとって母の象徴。そして、後から登場するヨークシャーテリアは弟や妹を表しています。
毛色が成長とともに変わるヨークシャーテリアは、見た目が変わらないテディベアとの対比としてもぴったりでした。
この物語は、私にとって“精神的な母子分離”を描いた作品です。
大人になった私が、幼かった頃の自分に寄り添い、「愛されてなかったわけじゃないよ」と伝えるために描きました。
たとえ大切な人とずっと一緒にいられなくても、その気持ちが変わらない限り、宝物のような存在であることは変わらない——
そんな想いをこめています。
この絵本はのちに英訳され、イギリスの展示会でも販売されました。
独身だった私が“子ども側の気持ち”だけで描きあげた物語ですが、インナーチャイルドと向き合った時間は、今の子育てにも深く影響を与えてくれていると感じています。


絵本の中で「これだけは大切にしている」というテーマや価値観があれば教えてください。
「絵本の主役は、読み手である子ども」ということです。
3. 子育てについて
お子さんとの日々の中で、どんな瞬間に喜びを感じますか?
2歳になっていろんなことができるようになったので、最近は一緒にパンやお菓子を作っています。
手作りだと砂糖の量や種類も調整できて安心ですし、何より一緒に作ったものを一緒に食べる時間がとても幸せです。
五感を使うお菓子作りは、母にも子どもにも良い効果があるように感じています。少し前に焼いたデニッシュも、とても美味しくできて喜んでいました。
一方で、子育てでつらかったことや大変だった経験はありますか?それをどうやって乗り越えてこられましたか?
つらかった記憶はあまりないですね。お菓子作りも大変ですが、失敗してもそれも楽しい遊びの一部です。
夫が頼りになるので、大変な時は遠慮なく甘えています。
私は娘の脳と骨格がしっかり育つように、特に背骨がC字からS字に発達する過程を意識しています。
つらいことも大変なことも、未来を創ると思って取り組んでいるので、苦に感じることは少ないです。
お子さんに伝えていきたいこと、大切にしている育児の軸があれば教えてください。
私は娘の自発性を大切にし、人格を尊重して共に生きています。
これは夫や自分自身にも同じことを意識しています。
娘は私とは違う人間で、違う時代を生き、違う人と出会います。
だからこそ、私は先回りせず娘の可能性を信じ、自分自身の可能性も信じて、自分の人生を生きる。これが私の育児の軸です。
現在、保育士の資格取得に向けて勉強中とのことですが、そのきっかけや想いもお聞かせください。
実は、以前から保育の専門学校に通おうとしたことがありましたが、絵を描くことが最優先だったため、保育士資格に対してはあまり気持ちが向かなかったんです。
娘が生まれてから、発達や栄養について学び、保育園で働き始めたことで、いよいよ保育士資格に挑戦しようと思いました。
夫の姿を見て、自分も資格を活かして働きたいと思ったのも理由の一つです。
そして何より、娘に学ぶことの大切さを伝えるためには、私自身が勉強している姿を見せることが大事だと思ったからです。
実際に学び始めると、自分がまだ知らないことだらけで、教育の重要性を再認識しました。
カンボジアでワークショップをした経験もあり、娘には学ぶ楽しさと世界を広げる力を感じてほしいと願いながら、勉強を楽しんで試験に取り組んでいます。
4. インスピレーションについて
どんなものや場所、人との出会いがインスピレーションになりますか?
想像できない場所との出会いは、強いインスピレーションを与えてくれます。
例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館でピカソの絵を見た時、小学生の頃に社会見学で見た絵を思い出し、過去の自分と対話するような不思議な感覚がありました。
フィンランドの一人旅では、トーベ・ヤンソンの壁画に心が震えるような感覚を覚え、絵の力を強く感じました。
心惹かれる絵に出会うと、自分も描きたくなる気持ちが湧いてきます。
現実の中に現れる非日常的な時間の心地よさは、ファンタジーの世界を創造する欲求とも繋がっていると思います。
子育て中の今だからこそ得られる創作のヒントや気づきがあれば教えてください。
娘が大好きな絵本『おやすみなさい おつきさま』を何度も読んでいて、暗唱するほど夢中になっている姿を見て、私自身の絵本の捉え方が変わりました。
リビングには絵本が300冊くらいありますが、娘はその中から選んで読んでいて、その姿は子育てしていなければ見られなかったものです。
繰り返し読むことで得られる安心感や、色彩がはっきりした絵本の魅力は、大人にも通じるものですが、子どもと大人の感性はやはり少し違うと感じました。この気づきは、子育て中だからこそ得られるものです。
ご自身にとって「美しい」と感じる瞬間はどんな時ですか?
自然が作り出す世界は美しいと感じます。絵を描いていると、自然の色彩は何層も重なり合っているように見えます。
グランドキャニオンの景色やハワイの海、グレートバリアリーフも美しく、蜂の巣のハニカム構造も素晴らしいです。形やバランスが調和しているのが自然の美しさだと思います。
そして、ナチュラルダイヤモンドも美しく、大好きです。
5. これからについて
今後挑戦してみたいことや、描いてみたいテーマはありますか?
一番やりたいのは、赤ちゃん絵本の制作です。シンプルさが難しく、なかなか完成できていません。
また、編集者に勧められた食べ物をテーマにした絵本では、ケーキを題材にして取材もしてきました。
それに加えて、森や動物との共生を描いた絵本や、人形職人とその人形の物語も考えており、少しずつ形にしていきたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。これまで三人のお客様のインタビューをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。これからも続きますのでどうぞお楽しみに。
母の日限定で、ブログを読んでくださったみなさまへ15%オフのクーポンをプレゼントいたします。
クーポンコード:DREAM
※セミオーダーを除くすべてのジュエリーが対象です。
※ご利用期限:2025年5月11日(日)23:59まで
この機会に、がんばるご自分へのご褒美として、心ときめくジュエリーをお迎えいただけたら嬉しいです。